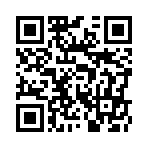2009年06月12日
☆過去の 記憶の匂い
過去の記憶の匂い
よく「過去の記憶を持っている」という言い方をすることがあります。
時間の流れは「過去」「現在」「未来」で捉えても、
記憶に関しては「過去のもの」という認識で、
「自分の中に未来の記憶を溜めている」とは全然思っていないことでしょう。
しかし実際、我々は未来についての記憶を相当溜めており、
その比率は思っているより高いというのが脳科学者たちの見解なのです。
記憶には、常に“過去の匂い”や“過去の色”のようなものがつきまといます。
記憶を組み合わせて何かを考えるとき、考えているのは「今」の自分でも、
その自分の考えにはどうしても過去の記憶の匂いがついてしまうものなのです。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)、いわゆるトラウマなどは典型的な例です。
過去の多大なストレスは現在の行動や情動に影響し、
けっこう支配力があるとということが広く知られています。
朝起きて、今日は嫌なことが起こりそうだと思ってしまうと、
特に何もなくても一日中気分が晴れないのは、「嫌なことが起こるかも…」
と予測した記憶に引きずられるからなのです。
望ましくない未来を思い描くと「嫌な記憶」になって「嫌な気分」を喚起します。
これを繰り返して「未来」が嫌な色に染め上がってしまうと、
明るい未来を思い描こうにも嫌な気分に引きずられて、
どんどん悲観的になるという悪循環を招くのです。
ところが、こんな記憶の作用が実は未来の計画にも影響を及ぼしていることに、
我々はあまり気づいていないのです。
新年に今年の目標を立てた人は多いでしょう。
「今年は!」「今年こそ!」と気分新たに誓いを立てたつもりなのに、
すでに雲行きが怪しくなってきたとしたら、それは記憶の仕業かもしれません。
ポジティブ色の「記憶貯金」をしよう!
たとえば、「今年は絶対にノルマを達成する」という目標を立てたとしましょう。
その意気込みはいいのですが、
根底にあるのが人前でこっぴどく自分を罵った上司への怒りや、
去年達成できなかったときの惨めさや、
今年も無理だったらどうしようという不安など後ろ向きな記憶ばかりだと、
目標を立てた時点ですでに過去のネガティブな色がついてしまっているのです。
言葉は前向きでも思い切りネガティブ色に染まった目標では、
嫌な過去を思い出すのとあまり変わりません。
気分が乗らないのも当然でしょう。
それなら、ノルマ達成→収入アップ→新車購入→周りの人も自分を見直す…、
という発想で、ネガティブ色の過去に影響を受けない
「新車を買う」を目標にしてみたらどうでしょう。
結果的にノルマ達成を目指すことになるし、
ついでに新車で彼女と楽しくデートする場面を想像しておけば、
ポジティブ色の「未来の記憶貯金」もできると言うわけです。
「未来の記憶」をネガティブ色にしておくと、
結局そのことを考えるだけで嫌になるという現象が起こります。
「ポジティブ思考」の組み立て方と同じですが、
今の自分のネガティブな発想だけでなく、過去の記憶のネガティブな色も、
未来の“つまずく石”になりえることを覚えておくといいでしょう。
もう一つ、記憶というものは不安定で、
非常にあいまいだということも覚えておきたいですね。
「記憶を引き出す」という言い方をするせいか、頭の中に記憶の箱があり、
必要に応じて何かを取り出すイメージがるでしょう。
記憶は「もの」のように固定的だと考えられがちです。
しかし、そもそも記憶とは脳の一種の状態なのです。
呼び出そうと思うときや、何かの気まくれでふと立ち上がってくるネットワークで、し
かも精密に再現性よく立ち上がるネットワークではないのです。
それっぽい「システム」が立ち上がるだけのことなのです。
続きは来週に・・・
よく「過去の記憶を持っている」という言い方をすることがあります。
時間の流れは「過去」「現在」「未来」で捉えても、
記憶に関しては「過去のもの」という認識で、
「自分の中に未来の記憶を溜めている」とは全然思っていないことでしょう。
しかし実際、我々は未来についての記憶を相当溜めており、
その比率は思っているより高いというのが脳科学者たちの見解なのです。
記憶には、常に“過去の匂い”や“過去の色”のようなものがつきまといます。
記憶を組み合わせて何かを考えるとき、考えているのは「今」の自分でも、
その自分の考えにはどうしても過去の記憶の匂いがついてしまうものなのです。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)、いわゆるトラウマなどは典型的な例です。
過去の多大なストレスは現在の行動や情動に影響し、
けっこう支配力があるとということが広く知られています。
朝起きて、今日は嫌なことが起こりそうだと思ってしまうと、
特に何もなくても一日中気分が晴れないのは、「嫌なことが起こるかも…」
と予測した記憶に引きずられるからなのです。
望ましくない未来を思い描くと「嫌な記憶」になって「嫌な気分」を喚起します。
これを繰り返して「未来」が嫌な色に染め上がってしまうと、
明るい未来を思い描こうにも嫌な気分に引きずられて、
どんどん悲観的になるという悪循環を招くのです。
ところが、こんな記憶の作用が実は未来の計画にも影響を及ぼしていることに、
我々はあまり気づいていないのです。
新年に今年の目標を立てた人は多いでしょう。
「今年は!」「今年こそ!」と気分新たに誓いを立てたつもりなのに、
すでに雲行きが怪しくなってきたとしたら、それは記憶の仕業かもしれません。
ポジティブ色の「記憶貯金」をしよう!
たとえば、「今年は絶対にノルマを達成する」という目標を立てたとしましょう。
その意気込みはいいのですが、
根底にあるのが人前でこっぴどく自分を罵った上司への怒りや、
去年達成できなかったときの惨めさや、
今年も無理だったらどうしようという不安など後ろ向きな記憶ばかりだと、
目標を立てた時点ですでに過去のネガティブな色がついてしまっているのです。
言葉は前向きでも思い切りネガティブ色に染まった目標では、
嫌な過去を思い出すのとあまり変わりません。
気分が乗らないのも当然でしょう。
それなら、ノルマ達成→収入アップ→新車購入→周りの人も自分を見直す…、
という発想で、ネガティブ色の過去に影響を受けない
「新車を買う」を目標にしてみたらどうでしょう。
結果的にノルマ達成を目指すことになるし、
ついでに新車で彼女と楽しくデートする場面を想像しておけば、
ポジティブ色の「未来の記憶貯金」もできると言うわけです。
「未来の記憶」をネガティブ色にしておくと、
結局そのことを考えるだけで嫌になるという現象が起こります。
「ポジティブ思考」の組み立て方と同じですが、
今の自分のネガティブな発想だけでなく、過去の記憶のネガティブな色も、
未来の“つまずく石”になりえることを覚えておくといいでしょう。
もう一つ、記憶というものは不安定で、
非常にあいまいだということも覚えておきたいですね。
「記憶を引き出す」という言い方をするせいか、頭の中に記憶の箱があり、
必要に応じて何かを取り出すイメージがるでしょう。
記憶は「もの」のように固定的だと考えられがちです。
しかし、そもそも記憶とは脳の一種の状態なのです。
呼び出そうと思うときや、何かの気まくれでふと立ち上がってくるネットワークで、し
かも精密に再現性よく立ち上がるネットワークではないのです。
それっぽい「システム」が立ち上がるだけのことなのです。
続きは来週に・・・
Posted by 花とも at 12:44│Comments(0)
│今日の言葉
この記事へのトラックバック
無意識で運動をした場合、その運動を実行したかどうかは、身体に証拠が残っていたり、
意識=予測と記憶【哲学はなぜ間違うのか?】at 2009年06月20日 23:30